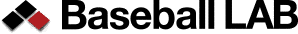ヤフオクドームの改修で影響を受けるホークスの選手とは? タイムリーdata vol.14
ソフトバンクの本拠地、ヤフオクドームの改修が発表されました。高さ4.2メートルの外野フェンスを既存のフェンスの前面に新設し、内部にホームランテラスと呼ばれるシートを設置。両翼100メートル、センター最深部122メートルに変更はありませんが、右中間と左中間は最大で5メートルほど短くなります。以前までウォーニングゾーンで捕球していた左中間、右中間への外野フライは大半が柵越え、もしくはフェンス直撃の打球になります。
球場が狭くなれば当然ホームランは増えます。球場の特性を表す指標として、パークファクターという数字があります。本拠地球場の相対的な本塁打の出やすさを表したもので、1.00を基準として大きいほど本塁打が出やすく、小さいほど本塁打が出にくい球場であることを示します。ヤフオクドームは直近3年間でいずれも1.00を大きく下回り、非常にホームランの出にくい球場だったということが分かります。
影響の及ぶ打者は?
ホームランは必ず1点以上入るため、得点数を競う野球において、本塁打数の多寡は投打ともに大きな影響を与えるといっても過言ではありません。まず、野手への影響についてですが、これは打球のタイプが関係します。どれだけ球場が狭くなったとしても、ゴロの打球がスタンドインすることは100%ありません。つまり狭くなった球場を最も生かせる打者というのは、フライをより多く打っている打者ということになります。
投手の場合も打球の性質が重要です。上記はソフトバンクの主力投手のゴロ/フライです。投手陣の中では森福允彦が極端なフライボーラーで、球場が狭くなった影響を受けやすいと推測できます。飯田優也もフライ性の打球が多く、影響を受ける可能性があります。一方でゴロの比率が高いウルフ、五十嵐亮太、武田翔太などはヤフオクドーム改修の影響をさほど感じさせることのない投球を続けてくれるでしょう。
そして投手にはどんな球場であろうとも、ほぼ確実にアウトを奪うことのできる手段があります。それは三振です。三振は振り逃げのケースを除き、野手の守備力や球場の広さを無視してアウトを奪うことができます。ゆえに奪三振率の高い投手は、狭くなった球場でも成績を維持しやすいと考えることができます。
圧倒的な奪三振率を誇るサファテは環境の変化による影響が少ないと考えられ、ゴロ比率の低かった飯田も高い奪三振率を維持できれば成績への影響を最小限にとどめることができそうです。五十嵐と武田はゴロ比率の高さのみならず、奪三振率でも高水準。彼らはどこの球場でも一定の内容が期待できるでしょう。
エンターテインメント性と強さの両立なるか?
昨年日本一のソフトバンクは、指揮官・秋山幸二の退任を受けて工藤公康新体制が発足。松坂大輔、バンデンハークら新戦力も加わっています。そんな中、孫正義オーナーの「ファンにより一層楽しい野球を」という意向により、外野フェンスを以前より前に配置し、ホームランテラスの増設が行われました。連覇のカギは、新しくなった球場の特性を選手たちがいち早くつかむことができるか?ということも大きな要素となりそうです。